
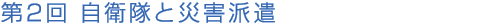

まず、航空救難団が所属する自衛隊について説明しよう。
自衛隊は、1954年に制定された自衛隊法に基づく組織で、防衛庁のもとに陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛大学校などの機関がある(法律上の定義では「自衛隊」というと、防衛庁などの背広組なども含まれる)。
そしてその任務は「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」(自衛隊法3条)というものである。
民主国家の原則として、軍事組織のシビリアン・コントロール(文民統制)というものがある。これは、第二次大戦前の日本にあったような、軍部による独裁政治(軍閥政治)などを回避するため、政治家や行政府(背広組)などが軍事組織(制服組)の行動を監督するというものだ。現在の日本もシビリアン・コントロールの原則に従っており、自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣がもっていて、自衛隊の定員・予算・組織や防衛出動などは国会によって承認されることになっているほか、各種の出動についても、背広組と呼ばれる文民の要請・承認が必要とされている。
自衛隊の出動については、他国による軍事的侵略に対処するための“防衛出動”、警察では対処できないテロリスト対策などに行なわれる“治安出動”(海上の場合は“海上警備行動”)、PKO協力法やイラク復興支援特別措置法に基づく“海外派遣”、“領空侵犯対応(スクランブル)”、そして“災害派遣”などがある。
災害派遣は自衛隊法第83条によって定められており、地震などの災害や遭難事故などが発生した場合に行なわれるもので、各都道府県知事や災害対策本部長などの要請を受け、防衛庁長官が命じて出動する。また「天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる」となっている(自衛隊法第83条第2項)。
『よみがえる空』の主役である救難隊は、事故に遭った自衛隊員を救出する出動以外は、災害派遣として出動することがメインであり、『よみがえる空』も災害派遣時に発生した出来事を中心にして描かれている。
実際の航空救難団は、山岳での遭難者捜索と救出、難破船の捜索と救出などのほか、離島などで発生した急患輸送を行なう場合もある。
2004年の活動では、7月の新潟・福島豪雨災害で、空自より航空機9機と約70名の人員が派遣されて181名を救出(陸上自衛隊とあわせると1,975名)。同7月の福井豪雨災害では航空機3機と約10名の人員が派遣されて54名を救出(陸上自衛隊とあわせると455名)。また11月に北海道小樽市沖で防波堤に衝突した貨物船から、航空機4機で乗組員15名を救助するなどの実績を上げた。そして当然ながら、死者40人、全壊家屋2867棟を出した2004年10月の新潟県中越地震にも派遣されている(陸海空自衛隊合計で約1,770名を救出)。このようにして彼らは、多数の人命を救ってきた。
| 災害名(2004年) |
出動航空機
(航空自衛隊) |
派遣人員
(航空自衛隊) |
救出人員
(航空自衛隊のみで) |
救出人員
(陸上自衛隊との合計) |
| 新潟・福島豪雨災害 |
9機 |
約70名 |
181名 |
1,975名 |
| 福井豪雨災害 |
3機 |
約10名 |
54名 |
455名 |
| 北海道小樽市沖 |
4機 |
- |
15名 |
- |
| 新潟県中越地震 |
派遣人員 127,300名(自衛隊合計) |
1,770名(自衛隊合計) |
|
|
そしてこれらの任務は、悪天候下などの危険な災害現場で行なわれるものであり、当然隊員に降りかかる危険も大きい。過去に何名もの殉職者を出しており、追悼して記念碑が建てられているところもある。まさに彼らは自らの命を危険にさらして、他の人々を救う任務に就いているのである。 |



